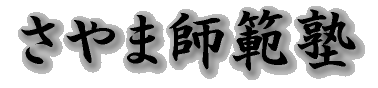
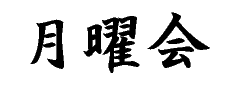 [ もどる ]
[ もどる ]
【基本】 教育の関する基本用語の確認(1) さまざまな教育用語について基本を確認しましょう。
最終更新日25.9.22
|
|
1 教育の目的とは
教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身共に健康な国民の育成を期して行わなければならない。
(教基法第1条)
2 教育の目標は
生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な 思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うこと。
(学教法第30条②)
3 生きる力
基礎・基本を確実に身につけ、いかに社会が変化しようと、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力、自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力などのこと。
(H8.7中教審答申「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について」)
4 いじめの定義
「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
(文科省「H19 児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」)
5 「学級がうまく機能しない状況」とは …学級崩壊
「子どもたちが教室内で勝手な行動をして教師の指導に従わず、授業が成立しないなど、集団教育という学校の機能が成立しない学級の状態が一定期間継続し、学級担任による通常の手法では問題解決ができない状態に立至っている場合」
*「学級崩壊」という呼び方は事態の深刻さを強烈に意識させる響きをもち、複雑な状況をじっくりと多面的に捉えていく姿勢を弱めてしまう危険をはらんでいるため、「学級がうまく機能しない状況」という呼び方をするようになっている。
6 「指導が不適切である」教諭等とは
知識,技術,指導方法その他教員として求められる資質,能力に課題があるため、日常的に児童等への指導を行わせることが適当ではない教諭等のうち,研修によって指導の改善が見込まれる者であって,直ちに後述する分限処分等の対象とはならない者をいう。
【「指導が不適切である」ことの具体的な例】
1 教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、学習指導を適切に行うことができない場合
(教える内容に誤りが多かったり、児童等の質問に正確に答え得ることができない等)
2 指導方法が不適切であるため、学習指導を適切に行うことができない場合
(ほとんど授業内容を板書するだけで、児童等の質問を受け付けない等)
3 児童等の心を理解する能力や意欲に欠け、学級経営や生徒指導を適切に行うことができない場合
(児童等の意見を全く聞かず、対話もしないなど、児童等とのコミュニケーションをとろうとしない等)
*指導改善研修(教特法25-2)
(文科省「指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドライン」h20.2.8.)
7 不登校(長期欠席)とは
何らかの心理的・情緒的・身体的あるいは社会的要因・背景により、子どもが登校しない、あるいはしたくともできない状況にあること。(ただし、病気や経済的理由によるものを除く)
長期欠席とは、不登校と分類される欠席以外、すなわち病気や経済的理由によるもの。
8 道徳教育の目標
学校の教育活動全体を通じて、道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うこと。
【関連】
第1章総則 第1教育課程の一般方針の2
・学校における道徳教育は、道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行うもの
・人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に
生かし、豊かな心をもち、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛し、個性
豊かな文化の創造を図るとともに、公共の精神を尊び、民主的な社会及び国家の発展に努め、他国
を尊重し、国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成する
ため、その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。
<内容>
1 主として自分自身に関すること。(5)
2 主として他の人ととのかかわりに関すること(6)
3 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること(3)
4 主として集団や社会とのかかわりに関すること(10)
9 特別支援教育とは
障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力の高め、生活や学習上の困難を改善、又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの。
(文科省「特別支援教育の推進について(通知)」の「特別支援教育の理念」H19.4.1)
10 子ども大学
地域の大学や市町村、企業・NPO、県が連携して、子ども(原則として小学校4~6年生)の知的好奇心を刺激する学びの機会を提供するもの。
1.ものごとの原理やしくみを追求する「はてな学」、2.地域を知り郷土を愛する心を育てる「ふるさと学」、3.自分を見つめ人生や将来について考える「生き方学」、の3つの分野の講義を基本に行う。学校とは一味違ったテーマを取り上げて、大学教授や地域のプロフェッショナルが教える。
平成23年度からは、「元気な地域を創造する子ども大学推進事業」として実施している。各子ども大学で行う開校事業と、子ども大学が合同で行う交流・連携事業がある。
*子ども大学は、ドイツのチュービンゲン大学で2002年に始まり、ヨーロッパでは、100校近い子ども大学が開設されている。埼玉県では、NPO法人子ども大学かわごえが2009年3月に「子ども大学かわごえ」が最初に開校した
(埼玉県のHPより)
11 支援籍
障害のある児童生徒が、必要な学習活動を行うために、在籍する学校または学級以外に置く、埼玉県独自の学籍のこと。 ①障害のない子にとっては、障害者に対する差別や偏見といった心の障壁が取り除かれる。② 障害のある子にとっては、異なる環境に対する適応力や、大きな集団での社会性が培われ、さらに地域とのつながりが広がる、等の効果が期待される。
(埼玉県のHPより)
12 ノーマライゼーション
「障害者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きることこそノーマルであるという考え」のこと。ノーマライゼーションの理念の実現を図るためには、障害のあるなしに関わらず、子どもの頃から共に育ち、共に学ぶことが大切になる。
埼玉県では、障害のある子とない子が一緒に学ぶ機会を拡大していくために、県独自の仕組みである「支援籍」の普及・定着を図るなど、「ノーマライゼーションの理念に基づく教育の推進」に取り組んでいる。
(埼玉県のHPより)
|
Since: 2012/4/26 さやま師範塾 月曜会
All Rights Reserved, Copyright (C) 2012, Sayama-city Education Guidance Division
Phone 04-2953-1111 Fax 04-2953-1132 (extension No.5652)
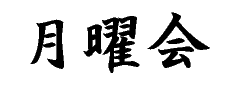 [ もどる ]
[ もどる ] ![]()
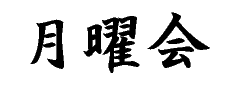 [ もどる ]
[ もどる ]