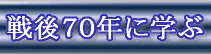 最終更新日 27.8.15.
最終更新日 27.8.15.日本が先の大戦で敗戦してから、今年で70年目にあたります。
[ふれあい講演会 被爆体験を語る (中島寿々江 氏)]
8月15日はどんな日なのだろう…
日本政府はこの日を「戦没者を追悼し平和を祈念する日」とし一般には「終戦の日」「終戦記念日」と
呼ばれています。一般にはこの日をもって、連合国との戦争が終わったように受け取られがちですが、
実際にはそう単純ではありません。
1945年7月26日、アメリカ合衆国を中心に作成されたポツダム宣言が出され、日本にこれを受け入
れるように求めてきました。
これを受けて政府や軍の代表が話し合いましたが、なかなか決断することできず、結局、天皇陛下の
「聖断」をもってこれを受け入れ、敗戦を認めることに決まりました。
政府は8月14日に連合国に対してポツダム宣言の受諾を通告し翌15日に有名な「終戦の玉音放送」
によって、天皇陛下自らが、国民にこのことを伝え、戦争を終結することが告げられました。
従って、
8月15日は、「日本がポツダム宣言を受入れ戦争を終えることを国民に伝えた日」ということになります。
これで戦争が終わったように思われがちですが、そうではありません。あくまでも、連合国に受諾を通告
し国民に戦争を終えることを伝えただけなので、正式に軍が戦闘を中止し、連合国が攻撃を止めた日と
いうわけではありません。実際に8月15日以降に戦死した軍人や民間人は多数います。
正式に、日本が降伏文書(戦争に敗けたことをみとめた文書)に調印したのは9月2日です。正式に
戦闘が終わったのはこの日ということになります。アメリカはこの日を、対日勝戦記念日(V-J DAY)に
しています。
さらに国際法上、完全に戦争状態が終わったのは、1951年9月8日にサンフランシスコ講和条約を
結び、この条約が効力をもった1952年4月28日ということになります。
またソ連(今のロシア)とは北方領土の問題等が解決していないこともあり、未だに講和条約を結んで
いないので正式に戦争が終わったとは言えない状態が続いています。
こんな勉強をしてみましょう。
◆教科書にある言葉を用語集で調べて、ノートに書き写す。
◆図書館などにある戦争を描いた本を読んでみましょう。ほんの一部を以下に紹介します。
(皆さんが感動したり、勉強になった本や映画、資料があったら教えてくださいね。)
◇戦争を経験した人の話などを聴いてみる。
◇戦争を記録した映画を観たり、記念館などに行ってみる。
◆疑問に思ったことなどは、調べたり、大人や先生に質問してみる。
◆今の社会が先の戦争の影響をどのように受けているか考える。
◆過去の教訓を、これからどう生かしていったらいいのか友達や大人と話し合ってみる。
|
<本> 『終わらざる夏』(集英社文庫) 浅田次郎 …徴兵の悲劇 『日本のいちばん長い日』 (文春文庫) 半藤 一利 …この夏映画化、ちょっと難しいかも 『人間の條件』(岩波現代文庫) 五味川純平 …満州、シベリア抑留 長編です。 『収容所(ラーゲリ)から来た遺書』(文春文庫) 辺見じゅん …シベリア抑留。読みやすい。 『永遠のゼロ』 (講談社文庫) 百田尚樹 …DVD有り 『野火』 (新潮文庫) 大岡 昇平 …この夏映画化。 『銃口』(角川文庫) 三浦綾子 …戦争への道 朝鮮人労働者 『少年H』(講談社文庫、新潮社文庫) 妹尾河童 …DVD有り 『15歳の東京大空襲』(ちくまプリマー新書) 半藤一利 …図書室にあります。読みやすい。 『ビルマの竪琴』 (新潮文庫) 竹山道雄 …有名な作品。児童向けで読みやすい。DVDもある。 『ラバウル戦記』(ちくま文庫) 水木しげる …ラバウル島での実体験、読みやすい 『出口のない海』(講談社文庫) 横山秀夫 …人間魚雷回天 『落日燃ゆ』(新潮文庫) 城山三郎 …広田弘毅、東京裁判。 <映画(レンタルで観られます)> 『東京大空襲 ガラスのうさぎ』 …東京大空襲 『きけわだつみの声』 …学徒出陣 『火垂るの墓』 …神戸大空襲・戦災孤児 『はだしのゲン』 …原爆 『太平洋の奇跡 フォックスと呼ばれた男』 …サイパン島 『硫黄島からの手紙』 …硫黄島 『樺太1945年夏 氷雪の門』 …ソ連侵攻、集団自決 『ひめゆりの塔』 …沖縄戦、集団自決 |
【勉強する上での注意】
・インターネットなどの情報には偏ったものや誤った記述が多く見受けられます。正しい知識を得るには注意が必要です。
・本や映画など、脚色や実際とは違う描き方をしているものも多いので、フィクションなのかノンフィクションなのかを確認しましょう。
|
【リンク】 |