| ―「思いがなければ、気づかないものがある」― | 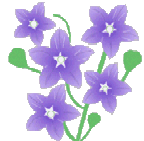 |
本校は学校教育目標に、「豊かな心をもち思いやりのある生徒」を掲げている。徳育の育成という
事であるが、評価するのが難しい目標でもある。何をもって豊かな心というのか、思いやりとは何な
のか、そのこと自体に実態がなく具体性がない。世界大百科事典によると、心とは、「知,情,意に
よって代表される人間の精神作用の総体,もしくはその中心にあるもの。」とある。「心を見たこと
があるか」と問われて「ある」と答える人はおそらくいないだろう。「心はどこにあるのか」と問わ
れたら・・・・・・。胸を指したり、頭を指したり、人それぞれのような気がする。それでも心はあ
ると皆が思うから言葉が存在しているのだろうと思う。
さて、難しいことはさておき、私が学校教育目標として掲げ、達成できたかどうかの判断をする視
点についてお話ししたいと思う。「豊かな心」とは「思いやり」と共に育まれるものである。誰かが
見ていなくても落ちているゴミを、さりげなく拾えるようになったとき、その人は「豊かな心」が育
まれていると考えられると思う。有名な短歌に
「秋きぬと 目にはさやかに 見えねども 風の音にぞ おどろかれぬる」
という一首がある。立秋の日に詠んだという歌。「立秋の日から風は吹き増さる」という当時の常識
―生活実感に基づく常識と言うよりも文学的な常識― を前提とし、「目に見る」「音に聞く」とい
う対比のもとに季節の推移への気づきを詠んだ短歌である。秋という目には見えないものを音によっ
て感じとる思いがなければ分からない感慨であると思う。
思いがなければ分からないことは身近にもたくさんある。例えば点字がいい例である。缶ビールの
プルタブの脇に
 という盛り上がった部分がある。何と書いてあるかお分かりだろうか。「おさけ」と書いてある。視
覚に障害のある方がお酒と、他の飲み物とが区別できるようにデザインされている。点字に興味がな
ければ、ただの突起。他の物に興味を持ち大切にし心配する。その思いがあった時にはじめて見えて
くるものがあるのだろう。
常に病気以外の生徒は学校に来て、元気に活動している。他人をいじめるような行為をする子など
いないので不登校の生徒はいない。清掃が行き届いているので校舎は清潔である。誰と会っても生徒
は自然な挨拶ができる。年長者を敬い、弱い者いじめなど決してしない。だから常に全力で学習に、
運動に励むことができる。生徒と教師は師弟の絆で結ばれ、互いを信頼し敬愛している。そんな思い
で、学校教育目標に「豊かな心をもち思いやりのある生徒」を掲げている。達成には時間がかかるか
もしれないが、達成に向けた足音は目には見えないけれども、確実に聞こえている気がする。
という盛り上がった部分がある。何と書いてあるかお分かりだろうか。「おさけ」と書いてある。視
覚に障害のある方がお酒と、他の飲み物とが区別できるようにデザインされている。点字に興味がな
ければ、ただの突起。他の物に興味を持ち大切にし心配する。その思いがあった時にはじめて見えて
くるものがあるのだろう。
常に病気以外の生徒は学校に来て、元気に活動している。他人をいじめるような行為をする子など
いないので不登校の生徒はいない。清掃が行き届いているので校舎は清潔である。誰と会っても生徒
は自然な挨拶ができる。年長者を敬い、弱い者いじめなど決してしない。だから常に全力で学習に、
運動に励むことができる。生徒と教師は師弟の絆で結ばれ、互いを信頼し敬愛している。そんな思い
で、学校教育目標に「豊かな心をもち思いやりのある生徒」を掲げている。達成には時間がかかるか
もしれないが、達成に向けた足音は目には見えないけれども、確実に聞こえている気がする。
|