| ―「 柿 日 和 」― | 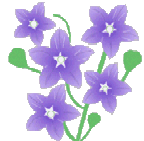 |
夏が去り、暑さにだらけていた心持が引き締まるのを感じると、本を読むとか勉強するとかいう、
内側に向いた気持ちが強くなってくる。頭がはっきりとしてくる季節は、生徒にとっては勉強には一
番適した季節だろう。
先日、英文学者の福原麟太郎氏の随筆を読んでいたら「柿日和」(かきびより)という言葉を目に
した。小春日和という言葉はよく聞くが、この柿日和という言葉には大変新鮮さを感じた。
「柿の実はよく熟れると半透明なコハク色になる。その柿を熟させた、ぽかぽか明るい秋の日和が
柿日和である。」とこの随筆には書かれていた。また、英国の詩人ジョン・キーツが書いた「秋に寄
せる頌」の詩の一説にある
season of mists mellow fruitfulness(霧と芳醇な実りの季節よ)の mellow なのが柿日和で
あるとも書かれていた。
私が小さい頃はあちらこちらの家の庭に柿の木があり、農家の庭先には柿が吊るしてあったりした
ものだが、こういった景色は、最近では目にすることは少なくなってしまった。
私の家の庭に一本の柿の木がある。私の祖父が生まれた時に、祖父の祖父が植えたものだと聞いて
いる。およそ120年の歳月が経っている。秋になると実を付ける。祖父は柿が好きで、よく食べて
いた。物静かな人で、人と人とが争うようなことは決して好まなかった。無口で温和な人柄で、まさ
にキーツが言う柿日和の「ぽかぽか明るい秋のような」人だったと思う。明治生まれの祖父のように
は、今の時代なかなか生きられないが、温暖化で短くなってしまった秋を有意義に過ごしたいとも思
っている。
福原氏は別の随筆の中で、秋をとらえる言葉を作っている。それは、「三四郎日和」(さんしろう
びより)というものである。夏目漱石の小説「三四郎」から命名したそうだ。
「風が女を包んだ。女は秋の中に立っている。」
作中に美禰子(みねこ)という女性が風に包まれた時の描写である。晩秋でしょうか。やはり、
ぽかぽかと日ざしの強い秋の季節を思わせるきれいな表現である。清澄な秋の空気が五感を通して感
じられる。
食欲の秋。読書の秋。温暖化の影響で、すっかり短くなってしまった秋をゆったりと過ごす中で、
子どもたちには、先人が言っている、「よく遊び、よく学べ。」であって欲しいと願っている。
|